こんにちは!めもりです。
今回はアクチュアリー2次試験(年金)の試験範囲を徹底解説します!
2次試験の勉強で使用する資料については以前紹介しましたが、年金1と年金2の切り分けは結構曖昧で、どちらか片方の合格を目指す場合は試験範囲を把握しておくことが合格の近道になります。
私も昨年は年金1のみの勉強でしたが、まず最初に試験範囲を理解するところから始めました。
年金の2次試験のうち1科目合格を目指す方にとって参考になるかと思います!
試験要領に記載されている試験範囲
まずアクチュアリー会が定める試験範囲をおさらいしておきます。(公式HP)
【年金1】
- 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の設計
- 確定給付企業年金制度および確定拠出年金制度の設計
- 退職金制度、中小企業退職金共済制度等
- 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)および各種退職給付制度の税務
【年金2】
- 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の財政
- 確定給付企業年金制度の財政
- 退職給付会計(国際会計基準を含む)
退職給付会計とDCは明確にわかれているためあまり気にしなくていいです。
過去に企業型DCの掛金の会計処理方法に関して年金2で出題されましたが、会計とDCを組み合わせた問題は非常に稀ですので例外と思っていいと思います。
問題はDBと公的年金です。
試験範囲を把握するうえで年金1の「設計」と年金2の「財政」の考え方が肝になります。
DB及び公的年金は年金1、年金2いずれも出題されますが、何も考えずに取り掛かると「この法令は試験範囲なのか?」と自問自答しながら試験を進めていく羽目になります。
実際、DBと公的年金の試験範囲は年金1と年金2で明確に線引されておらず、重複部分(年金1、2どちらで出題されてもおかしくない分野)が存在します。
ただ、なんとなく出題傾向を把握しておくだけでも不要な学習を削減できます。
2次試験の構成
次に年金の2次試験の構成について簡単に解説します。
試験は第Ⅰ部(50点)、第Ⅱ部(50点)の2部構成です。
第Ⅰ部は主に知識問題、第Ⅱ部は計算問題や所見が出題されます。
合計60点以上で合格となりますが足切りがあり、第Ⅰ部は30点、第Ⅱ部は20点を下回るとその時点で不合格となります。
以下では第Ⅰ部と第Ⅱ部に分けてDBと公的年金の試験範囲の違いを中心に解説します。
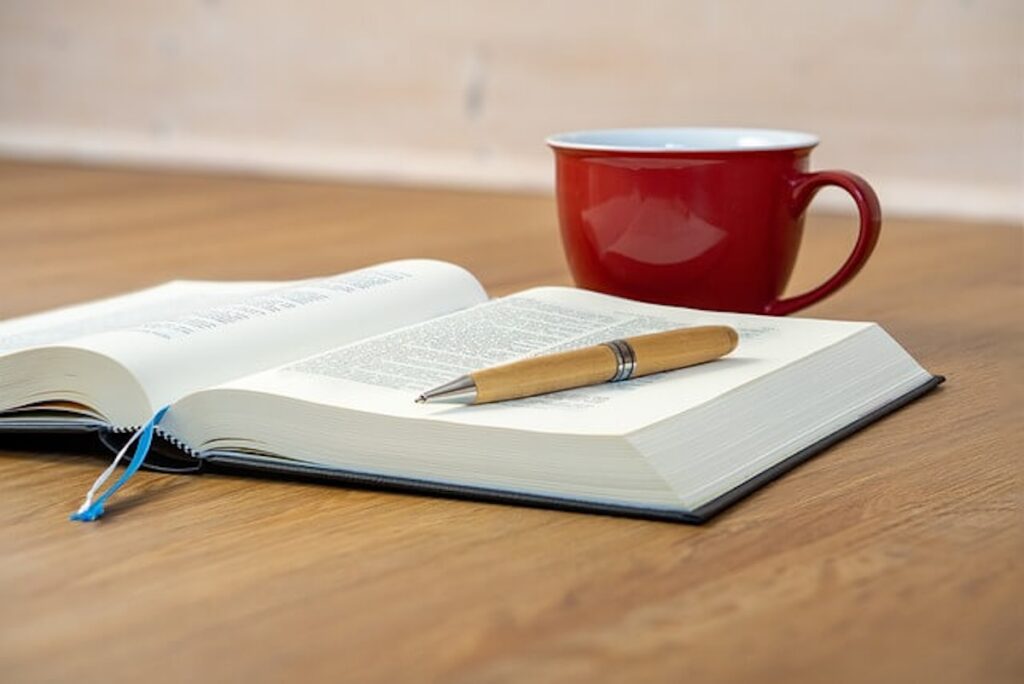
年金1、2の第Ⅰ部の試験範囲の違い
第Ⅰ部は年金1、年金2ともに知識問題が出題されます。
法令の穴埋めや正誤問題、簡記問題等です。
DBと公的年金については、先ほども言いましたが年金1の「設計」と年金2の「財政」の意味合いをなんとなく理解しておくことが重要です。
一言でいうと、「設計」とは給付額に影響がある内容、「財政」とは掛金に影響がある内容になります。
例えば、DBの給付減額の同意取得は給付額に影響するものですので主に年金1から出題されます。
一方で特別掛金やリスク対応掛金の算定方法は、掛金に影響がある内容ですので主に年金2で出題されます。
ただ、公的年金の場合は掛金と給付がDBよりも密接に関連しているのでより線引が難しいですが、財政検証レポートが年金2からのみ出題されます。そのため、公的年金を学習する際は設計と財政の違いを意識しながら、年金1の場合は企業年金に関する基礎資料や教科書、年金2は財政検証レポートを中心に学習していくのが良いと思います。
年金1、2の第Ⅱ部の試験範囲の違い
試験問題後半の第Ⅱ部は大きく2つに分けられます。
コンサル(計算)問題と所見です。
コンサル問題と計算問題
第Ⅱ部の10点分はコンサル問題もしくは計算問題です。
年金1ではコンサル問題、年金2では計算問題がほぼ確実に出題されます。
コンサル問題ではDBの合併やDC移行に際し、留意点や必要な同意、掛金への影響など実務においてアドバイスすべき内容を総合的に理解しているかが問われます。
計算問題も同様にDBの制度変更が題材とされることが多いですが、主に債務や掛金の計算など数値を算出する問題が出題されます。
どちらかというと、年金2の計算問題のほうが対策はしやすいと感じます。合格へのストラテジーで計算問題の演習はできますし、やり方さえ覚えれば解ける問題も多いためです。
コンサル問題は計算問題よりも幅広い知識が必要となるため、実務に携わっていなければ回答が全く書けないということもあります。過去問を解くか、実務に携わることしか対策のしようがない気がします。
所見
所見は40点満点です。基本的に1題20点満点の所見が2題出題されます。
所見は年金制度に関する自らの意見を述べるものであり1題あたり1,500字以上は書きたいところです。
所見についても主に年金1は給付額に関する題材、年金2は掛金額に関する題材が出題されることが多いです。
ただ、細かい暗記を求められるものではないため、ある程度自らの考えを述べることができるようになれば年金1、年金2いずれの問題でも1題あたり1,500字くらは書けるようになります。
対策としては過去問で傾向を把握しつつ文章力をつけていくことが重要だと思います。
DBの条文の出題箇所
DBの試験範囲について少し深堀りします。
法令のどの部分が該当するのか簡単にまとめました。
第一章 総則〜第三章 加入者
年金1、2いずれも出題される可能性あり
第四章 給付
年金1で出題される可能性が高い
第五章 掛金
年金2で出題される可能性が高い
第六章 積立金の積立て及び運用
積立金の積立ては年金2で出題される可能性が高い
積立金の運用は年金1、2いずれも出題される可能性あり
第七章 行為準則
ほぼ出題されない
第八章 確定給付企業年金間の移行等〜第十章 確定給付企業年金の終了及び清算
年金1、2いずれも出題される可能性あり
また、参考資料である数理実務ガイダンスの内容は主に年金2で出題され、法令解釈は年金1で出題されることが多いです。
最後に
まとめると、年金1、年金2いずれも合格されていない方はごちゃごちゃ考えるのが面倒なのでまとめて合格を狙ってください!笑
2科目合格は難易度は高いものの、共通部分があるので片方を勉強するのはあまり効率的ではありません。
また、数理人試験では年金1の知識も年金2の知識も必要となるので、ひとまず数理人試験まではまんべんなく勉強することをおすすめします!
ご拝読いただきありがとうございました!
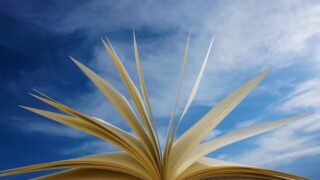

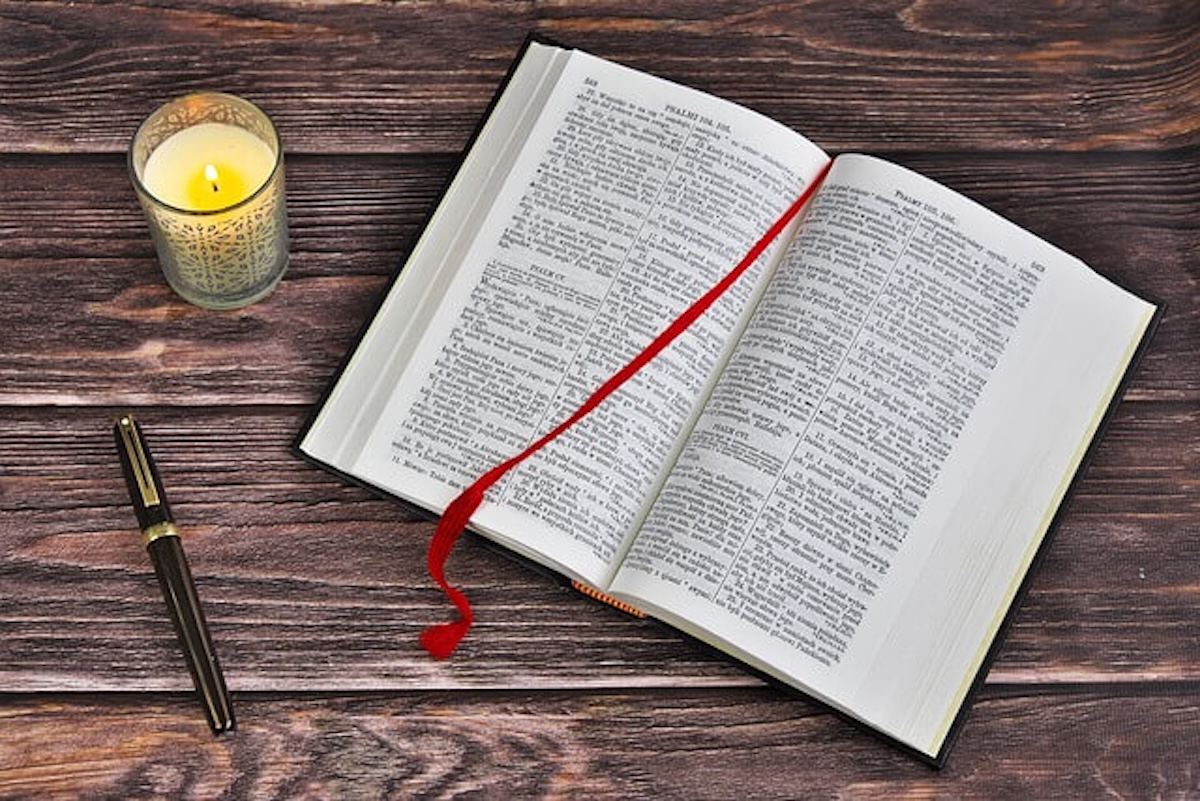



コメント